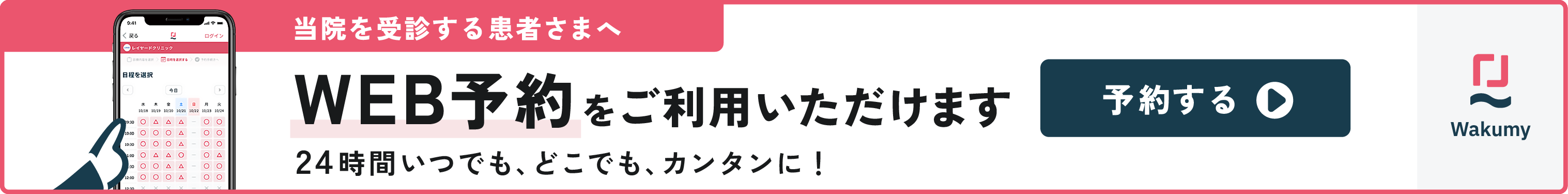消化器内科とは

消化器とは、口、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肛門という、全長9mにも及ぶ消化管と、唾液腺、肝臓、胆のう、膵臓といった付属器官のことを指します。それらの器官における疾患を診療するのが消化器内科です。疾患の原因は、風邪などのウイルス感染症に起因するものから、炎症性のもの、良性・悪性の腫瘍、機能性疾患、免疫システムの異常など多岐にわたり、体調不良で内科を受診される患者さんの中には、消化器系の疾患である場合が多くみられます。
消化器内科では、検査法について様々な方法が確立されており、胃内視鏡検査(上部消化管内視鏡検査:胃カメラ)、大腸内視鏡検査(下部消化管内視鏡検査:大腸カメラ)、腹部超音波検査(エコー)などが行われ、検査の際に患者さんにかかるストレスも軽減されるようになってきています。当院ではこれらの検査機器も十二分に活用しつつ、ひとりひとりの患者さんと丁寧にコミュニケーションを取りながら、診療を進めていきますので、以下のような症状がありましたら、お気軽にご受診ください。
消化器内科を受診される患者さんのよくある症状
- お腹の調子が悪い
- 胃が痛い
- 胃もたれがする
- 吐き気がする
- 胸やけがする
- 便秘気味である
- 便意が突然襲ってくる
- 下痢を繰り返す
- 血便が出た
- 食欲が無い
- 急に体重が減少した
- 顔色が悪いと言われる
たとえば同じ腹痛であっても、投薬等の治療によって改善する軽症のものから、がんのように放置しておくと重篤化する疾患まで様々です。不安を解消するためにも、また早期発見・早期治療のためにも、何らかの症状を感じたら、早めのご受診をお勧めします。
特に胃がん、大腸がん、膵臓がん、肝臓がんなどの消化器系のがんは、日本人のがん死亡数の常に上位に位置しています。胃内視鏡検査や大腸内視鏡検査、腹部超音波で検査することは、がんの早期発見には非常に有効な手段です。がんの早期発見のためには、症状のない方でも定期的な内視鏡検査、腹部超音波検査をお薦めしています。また当院では、胃がんの原因ともなるとされているヘリコバクター・ピロリ菌の検査も行っていますので、ご相談ください。
消化器内科で扱うことの多い主な疾患
- 逆流性食道炎
- 食道カンジダ症
- 急性胃炎
- 慢性胃炎
- 胃・十二指腸潰瘍
- ピロリ菌感染症
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 機能性ディスペプシア
- 感染性胃腸炎
- 腸閉塞症(イレウス)
- 急性腸炎(虫垂炎、憩室炎、虚血性腸炎など)
- 胃アニサキス症
- 便秘症
- 下痢症
- 炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)
- 脂肪肝
- 急性肝炎
- 慢性肝炎
- 肝硬変
- 胆石
- 胆嚢炎
- 胆嚢ポリープ
- 急性膵炎
- 慢性膵炎
- 咽頭・食道がん(扁平上皮がん)
- バレット食道がん(腺がん)
- 胃がん・胃線種
- 十二指腸がん・十二指腸腺腫
- 大腸がん
- 肝臓がん
- 膵臓がん
- 胆道がん・胆嚢のうがん
逆流性食道炎とは
逆流性食道炎は、「胃食道逆流症」の一つで、胃の内容物、主に胃酸が食道に逆流することによって食道に炎症が引き起こされる病気です。健康な場合でも逆流のみられることがありますが、短時間のため炎症は起こりません。逆流の時間が長くなることにより、胃酸に弱い食道の粘膜が炎症を起こし、発症します。直接、命に関わるような病気ではありませんが、食事を楽しめなくなったり、夜、眠れなくなったりしてしまいます。また逆流性食道炎を繰り返すことにより、食道がん(バレット食道がん)につながるリスクが高まると言われています。
原因としては食道と胃の境目にあって、食物の通過時以外は胃の入り口を絞めて逆流を防いでいる、下部食道括約筋が緩んでしまうことによるとされています。緩む原因としては、加齢や、食べ過ぎ、早食いによる胃内圧の上昇、肥満や衣服の締め付けによる腹圧の上昇、脂肪分の多い食事、またアルコールや喫煙なども括約筋が緩む原因にあげられます。さらに胃酸が最も多く出る食後すぐに横になってしまったり、農作業等で前かがみの姿勢を取り続けたりすることも、逆流性食道炎の原因になります。
逆流性食道炎の症状として代表的なものは胸やけです。みぞおちのあたりから胸にかけて、焼けつくような、あるいは熱くなるような不快な感覚が現れます。ひどい時にはのどまで上がってくる「呑酸(どんさん)」という感じがあり、痛みを伴う場合があります。のどの不快感や、痰を伴わない咳が出たり、げっぷがよく出たりといった症状もみられます。こうした症状が気になったら、逆流性食道炎かもしれません。また、突然胸の痛みを感じる場合もあり、心臓疾患かと思ったら、逆流性食道炎が原因だったという例もあります。
胃酸の逆流が繰り返され、食道が胃酸にさらされる食道炎が長期間続くと、より重症な状態になるリスクがあります。食道の内壁がただれる食道の潰瘍や食道狭窄(食道が狭くなること)、さらにはバレット食道と呼ばれる食道の細胞変化が起こり、食道がん(バレット食道がん)のリスクが高まる可能性もありますので、注意が必要です。
診断にあたっては、まず問診で胸やけなどの症状の有無をお伺いし、逆流性食道炎が疑われる場合は、投薬などの治療を行いますが、症状が改善しない場合や、他の病気が疑われるときは、胃内視鏡検査を行い、診断を確定する場合もあります。
逆流性食道炎の治療は、胃酸を抑えることが第一となりますので、PPI(プロトンポンプ阻害薬)や、P-CAB(カリウムイオン競合型アシッドブロッカー)などの胃酸分泌抑制薬を使用します。また食道狭窄がある場合はバルーンによる拡張を行ったり、炎症が続き場合は手術が必要となることもあります。
逆流性食道炎を予防したり、また繰り返し引き起こさないようにするためには、生活習慣の改善も重要になります。以下の点に気を付けましょう。
- 食べ過ぎや早口を避ける
- 脂っこいものや柑橘系、甘味(あんこ等)やアルコール、炭酸飲料をなるべく控える
- 肥満の人はなるべく減量する
- 禁煙する
- 食後2~3時間は横にならないようにする
- 夜間に症状が出る人は枕を高くして寝る
- 腹部をベルトや服で締め付けないようにする
- 長時間の前かがみの姿勢はなるべく避ける
逆流性食道炎は放置しておくと生活の質を低下させてしまいます。しかし、治療することによって、大きく改善する病気でもありますので、早めのご受診をお勧めします。
胃・十二指腸潰瘍とは
胃・十二指腸潰瘍は、併せて消化性潰瘍とも呼ばれる疾病で、胃液によって胃や十二指腸の壁に炎症が起こるものです。本来、胃や十二指腸の壁は、胃液によって傷つけられないよう、粘膜で防御されています。この粘膜によるコーティングが、何らかの理由で破られてしまうと、胃液によって炎症が起こってしまいます。炎症が悪化し、傷が深くなってしまうと、壁に穴が開く胃穿孔や十二指腸穿孔を引き起こし、緊急手術が必要となってしまう場合もあります。
以前は胃潰瘍というと、暴飲暴食やストレスが原因とよく言われていましたが、現在では大きく2つの原因がわかっています。その一つが、ヘリコバクター・ピロリ菌への感染です。
ヘリコバクター・ピロリ菌は60歳以上の日本人では約半数が感染していると言われています。とくに高齢者になるほど感染率が高いと考えられています。このピロリ菌はウレアーゼという酵素によって、胃の中にある尿素を、アンモニアと二酸化炭素に分解し、このアンモニアによって胃酸を中和して、強い酸性である胃の中で生き延びるという特性を持っています。このアンモニアが胃や十二指腸の粘膜に作用し、粘液量が低下、粘膜が胃酸にさらされることになり、炎症や潰瘍が発症してしまいます。このピロリ菌が原因となっているのは、胃・十二指腸潰瘍全体の7~9割に及びます。
またヘリコバクター・ピロリ菌は胃がんのリスクを高めることでも知られています。当院ではピロリ菌検査を行っており、菌が認められた場合はピロリ菌の除菌治療も行っています。
胃・十二指腸潰瘍のもう一つの原因としてあげられているのが、非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)の使用によるものです。これは解熱、鎮痛、抗炎症のための薬剤で、リウマチや関節の痛みの治療や、脳梗塞や心筋梗塞の再発予防に抗血栓薬として使われるものです。しかし、胃の粘膜の防御する働きを抑えてしまうという副作用もあります。それにより胃・十二指腸潰瘍が引き起こされる場合があるのです。長期にわたって非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)を服用する必要のある患者さんは、制酸剤を併用するなどの注意が必要です。
症状としては、最も多いのがみぞおちのあたり(心窩部)の鈍い痛みです。特に空腹時に痛みが強まり、食事をとると軽くなることが多いとされています(ただし十二指腸潰瘍は空腹時に痛むことが多い)。これは他の消化器疾患と異なる点なので、診断の際の目安の一つとなります。この他にお腹の張りや吐き気、嘔吐、胸やけ、食欲不振などの症状が見られます。
潰瘍が進行し、深くなっていくと、血管を傷つけ出血がみられるようになります。そうすると吐しゃ物や便に血が混じるようになります。大量に出血した場合は、吐しゃ物は吐血という状況に、便はタール便と呼ばれる黒い便になります。ただし、人によっては、このような状況になるまで、痛みを感じなかった、という場合もあるので、注意する必要があります。
胃・十二指腸潰瘍と疑われる症状がある場合、胃内視鏡検査(上部消化管内視鏡検査)を行い、診断を確定させていきます。その際、出血があり、緊急に止血の必要がある場合は、同時に止血処理を行います。また、がんが原因で潰瘍を作る場合もありますので、病変部位から組織を採取して、良性か悪性かなどを検査します。
治療としては、胃酸の分泌を抑える薬として、プロトンポンプ阻害薬やH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)を内服します。さらに非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)を服用している場合はこれを中止し、必要に応じて他のタイプの消炎鎮痛薬に切り替えます。また、やはり暴飲暴食やストレスは胃酸の分泌を促進してしまう場合があるので、再発を防ぐ意味でも、食事に気を付けるとともに、喫煙やアルコールを控え、適度な運動をしてストレスを溜めないようにして、しっかりと治療を続けることが大切です。
感染性胃腸炎とは
胃や小腸、大腸の粘膜に炎症が生じ、腹痛や下痢、嘔吐を中心とした症状を起こす病気のことを、総称して胃腸炎と呼びますが、その多くがウイルスや細菌による感染性胃腸炎です。また胃アニサキス症など寄生虫によるものもあります。ちなみに非感染性の胃腸炎としては、薬剤や化学物質(キノコの毒やフグの毒なども含まれます)、ストレス等によるものがあります。
ウイルス性の胃腸炎としては、代表的なものにノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスがあります。ノロウイルスは、毎年11月~1月ころに流行し、激しい下痢や嘔吐などの症状があります。主に人の手指や生ガキなどの食品を介して感染し、その感染力が強いのが特徴です。成人だけでなく、乳幼児にも流行することがあり、脱水症状やけいれんなどの症状を引き起こす場合もあります。また体力の低下した高齢者においても重症化の危険があり、注意が必要です。
ロタウイルスによる感染性胃腸炎は乳幼児、小児によく見られます。やはり下痢や嘔吐の症状があり、水様で、白い便になることもあります。39度を超える熱が出る場合もあり、高度の脱水症状となることもあります。小児の感染性胃腸炎での入院の半数超がロタウイルスによるものだと言われており、腎不全や脳炎、けいれんなどの合併症を生じ、後遺症を残す危険性もある病気です。
ウイルスによる感染性胃腸炎の治療では、これに根本的な治療薬は存在せず、症状を和らげる薬を用います。ほとんどが自然に治るものですが、重篤な症状につながってしまう脱水症状を避けることが第一に重要になります。特に小児では経口補水療法が推奨されており、水分・塩分・糖分などの配合バランスが調整された飲料を、嘔吐に気を付けながら、少しずつ口から飲ませることで、脱水症状の改善と予防を図ります。ただし、脱水が進んでいる場合は点滴などが必要になります。
なお、ロタウイルスに関してはワクチンによる予防が有効です。初回の接種(トータルで2または3回接種が必要)を生後2月から14週6日までに受けることが推奨されています。
症状を和らげる薬としては、整腸剤や吐き気止め(ドンペリドン等)、解熱剤(アセトアミノフェン等)を使用する場合があります。小児に処方する場合は、用法や用量を注意して行います。下痢止めに関しては処方されることが少なくなっています。これは腸の中のウイルスを出してしまう方がよい、という考えからです。
感染性胃腸炎のもう一つの大きな原因として、細菌の感染があります。原因となる細菌としては、O-157などで知られる病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌(豚肉、鶏肉、殺菌が不十分な水)、腸炎ビブリオ(刺身、すし類)カンピロバクター(加熱不十分なタナゴ、鶏肉)などがあげられます。病原性大腸菌や黄色ブドウ球菌は、細菌が作る毒素が原因となります。
症状としてはウイルス性と同様のものが多いのですが、大腸菌の中でもO-157などの腸管出血性大腸菌では血管を壊す毒素を出すため、便に血が混じる場合(血便)があります。さらに重症化すると溶血性尿毒素症候群を発症し、腎臓の機能低下を招き、命に関わる場合があるので注意が必要です。
細菌による感染性胃腸炎の場合は、脱水症状への対策をはじめ、ウイルス性のものと同様の治療を進めるとともに、抗菌薬により回復を早めることが可能です。その場合、細菌によって効く抗菌薬が異なります。ただし現在は、高熱や激しい下痢、血便があるなどの重い症状でなければ、なるべく抗菌薬は使用しません。これは抗菌薬が効かなくなる薬剤耐性菌の増加を防ぐためのものです。
感染性胃腸炎は、予防してなるべく罹患しないようにするのが望ましい病気です。感染経路としては、ウイルスや細菌が付着したものに触ってしまう接触感染や、間接感染の咳やくしゃみ、糞尿が乾燥し空気中に漂ったものを吸い込んでしまう飛沫感染が考えられます。人が多く集まる場所ではマスクを着用するようにし、何かに触ったらアルコールなどで消毒することが大切です。ただし、ノロウイルスやロタウイルスはアルコールでは死滅しないので、次亜塩素酸ナトリウムを使用するか、石鹸でしっかりと手を洗うことが重要です。家族に感染者が出た場合は、タオルなどの共用を避け、ドアノブやおもちゃなどの消毒をする必要があります。また吐しゃ物や糞尿のついたおむつの処理をきちんと行いましょう。
過敏性腸症候群(IBS)
消化管粘膜などに器質的な異常(炎症などの目に見える、もしくは物理的な異常)が認められないにも関わらず、本来の健康的な消化管としての機能に障害があらわれる病気を、機能性消化管疾患といいます。それが大腸にみられるのが過敏性腸症候群(IBS)です。胃に現れた場合は機能性ディスペプシア(FD)と診断されます。
過敏性腸症候群は、ストレスや自律神経の乱れによって、腸の働きに異常が生じ、便秘や下痢など排便の異常をきたす病気で、日本人の約10%は過敏性腸症候群であるとされています。下痢が慢性的に続いてしまったり、便秘と下痢を数日ごとに繰り返したり、中にはトイレから離れられないといった様々な症状がみられます。器質的な異常がないことから、なかなか周囲に病気のつらさをわかってもらえないというケースもあります。
過敏性腸症候群の発症の原因は、まだはっきりとはわかっていませんが、ひとつには脳と腸の関係によるのではないかと言われています。ストレスがかかると、腸の動きをコントロールする自律神経に乱れが生じ、腸の動きが活発になりすぎたり、逆に鈍くなったりして、下痢や便秘になると考えられます。さらに腸の痛みを感じる知覚神経が鋭くなることで、お腹の痛みや張りを感じやすくなると考えられています。
ストレスの他に、感染性胃腸炎にかかった後に、発症するケースが多いことも知られています。胃腸炎が治ったように見えて、実はまだ軽い炎症が残っており、腸が過敏な状態になっているからであると言われています。さらに胃腸炎によって腸内細菌のバランスに異常が生じ、善玉菌が減って悪玉菌が増えると、腸が過敏になるとも言われています。
症状としては、腹部の痛みや不快感に加え、下痢、便秘、あるいは両方の混合した症状がみられます。下痢型はストレスや緊張で発症し、通勤途中でトイレに行けないときなどに起こりやすいとされています。また便秘型は便秘に伴ってお腹の張りがあり、混合型は便秘と下痢を交互に繰り返すことが特徴です。このような症状を、以下のような国際的な基準に照らし合わせ、当てはまる場合に過敏性腸症候群と診断します。
- IBSのRomaⅣ診断基準
- 最近3カ月間、月に4回以上腹痛が繰り返し起こり、次の項目の2つ以上があること。
1. 排便と症状が関連する(排便すると症状が和らぐ)
2. 排便頻度の変化を伴う(症状とともに排便の回数が増減する)
3. 便正常の変化を伴う(便の形状が柔らかくなったり硬くなったりする)
期間としては6カ月以上前から症状があり、最近3カ月間は上記条件を満たすこと
また診断に際しては、他の病気である可能性をきちんと否定しておくことも大切ですので、腹部エックス線検査や大腸内視鏡検査により、過敏性腸症候群同様、便通の異常を引き起こす大腸がんや大腸ポリープ、炎症性腸疾患、腸閉塞などの異常の有無を調べます。また腸の炎症を調べるため、血液検査を行う場合もあります。
過敏性腸症候群の治療は、生活習慣の調整と食事療法が基本となります。規則正しい生活をし、十分な睡眠をとって、刺激物や脂肪の多いもの、夜間に過食することは避けるようにします。症状が重く、つらい場合は薬物療法を行います。使用する薬としては、過敏性腸症候群治療薬としてポリアクリル樹脂経口薬があります。これは消化管内で水分を吸収し、内容物の動きを調節することで、下痢や便秘を抑える働きをもっています。下痢を改善するためには、セロトニン3受容体拮抗剤なども用います。また抑うつなど精神的な要因で改善がみられない場合は、心療内科での治療が必要な場合もありますので、まずはご受診いただき、ご相談ください。
腸閉塞症(イレウス)
イレウスとは何らかの原因で十二指腸、小腸、大腸という一連の腸管において、食物や胃液、腸液やガスなどの内容物が肛門まで移動するのが障害される状態をいいます。原因により、機械的イレウスと機能的イレウスに分類されます。
機械的イレウスは腸管が細くなったり折れ曲がったりすることで、腸管の内容物が流れにくくなっているものです。原因として、最も頻度が高いのが「癒着性イレウス」で、イレウス全体の6割近くを占めていると言われています。過去に腹部を手術した既往があったり、腹部の外傷や、胃潰瘍穿孔による腹膜炎の既往がある方が、その影響で腸管が他の臓器などに癒着し、発症する可能性が高くなっています。次に多いのが大腸がんなどの腫瘍によるものです。まれに便秘が続いて便がたまり硬くなって石のようになり(糞石)、それが詰まって閉塞する場合もあります。機械的イレウスの中でも腸管の血行障害を伴ったものは絞扼性イレウスと呼びます。そのままにしておくと腸管が壊死してしまい、重篤な状態になりやすく、緊急手術が必要となる場合もあります。
機能的イレウスは、腸管が麻痺を起こしたり、けいれんしたりすることで、腸管の内容物が流れなくなる状態を指します。特に麻痺によるものが多く、こちらも腹部の手術後や何らかの炎症により、腸の蠕動運動が低下して引き起こされます。緩和ケアに用いるモルヒネなどの麻薬性鎮痛剤が原因となる場合もあります。
イレウスの症状としては、激しい腹痛、吐き気、嘔吐、お腹の張り、便やおならが出ない、しゃっくりが出る等があります。絞扼性イレウスでは急激に発熱や激痛、脱水、血圧低下、意識障害が起こり、非常に危険な状態になります。
診断に際しては問診をし、腹部の手術歴の有無、イレウスに今までにもなったことがあるか、さらには便秘や嘔吐などの症状について伺います。イレウスの場合、嘔吐後に症状が軽くなることがあるのが特徴です。さらに腹部エックス線などを使い、腸管の拡張やガス像、閉塞部などを確認します。さらに脱水症状を起こしていないか、絞扼性イレウスの兆候がでていないかなどを血液検査によって確認します。
イレウスの治療には保存的治療と手術による治療がありますが、いずれの治療も早急に開始する必要があります。当院では問診や画像診断等で診断を行い、イレウスと診断、もしくはイレウスが疑われた場合でも、提携している医療機関と連携し、迅速な対応を行いますので、異常を感じた場合には早めにご受診ください。
消化器がんの発がん危険因子
日本において、がんは1981年から死因の第一位で、総死亡数の3割を占めています。発がんの機序は複雑で解明されていない部分が多いですが、日常生活の中における発がんの危険因子は徐々に解明されてきています。その危険因子を回避することは、発がんのリスクを減らす1次予防につながります。ただし、1次予防だけで発がんを完全に予防することは困難なため、早期発見・早期治療のための2次予防(定期的な検査)を行うことも重要です。
消化器がんの危険因子も明らかになっているものがいくつかあります。可能な限りリスクを減らす生活習慣を心がけ、危険因子を有する人は定期的な検査を行うことが推奨されます。
咽頭・食道がん(扁平上皮がん)
- アルコール
- 喫煙
- 熱い飲食物の摂取
咽頭と食道の粘膜は、どちらも扁平上皮細胞という同じ細胞で出来ているため、咽頭と食道両方にがんが発生する事(重複がん)があります。罹患数は微増傾向ですが、死亡数は減少傾向にあります。
アルコールは、胃や小腸で吸収された後に肝臓でADH(アルコール脱水素酵素)によってアセトアルデヒドに分解され、ALDH(アセトアルデヒド脱水素酵素)によって無害な酢酸(お酢)に代謝されます。しかし、日本人の約半数の人は、酵素の欠損によってアルコールを十分に代謝できない、もしくは全く代謝できない体質です。アルコールが代謝されないことにより、二日酔いの原因となるアセトアルデヒドが蓄積します。飲酒で顔が赤くなる“フラッシャー“も、このアセトアルデヒドが原因で、更に発がんの危険因子であることも分かっています。血液中濃度より唾液中濃度の方が10倍高いことから、咽頭がんや食道がんの原因になると言われています。お酒を鍛えて、顔が赤くならなくなった人でも同様です。お酒そのものにもアセトアルデヒドは含まれていますので、顔が赤くならない人でも、大酒家の人は発がんのリスクがあります。飲酒しない人に比べ、飲酒者で約3倍、食道がんリスクが上昇します。 日本酒にして2合以上飲酒する人は約5倍リスクが高まります。なお、日本酒1合と同じアルコール量は、焼酎で0.6合、泡盛で0.5合、ビールで大ビン1本、ワインでグラス2杯(200ml)、ウイスキーダブルで1杯です。アルコール代謝能力は測定できるものではなく、また個人差があるものです。必要以上の飲酒は控えることが咽頭・食道がんを予防することにつながります。
喫煙も咽頭がん・食道がんの大きな危険因子です。現在喫煙者だけでなく禁煙した人でも非喫煙者に比べ3〜4倍リスクが高く、しかも喫煙指数が高ければ高いほどリスクが上昇することが確認されています。
飲酒と喫煙には相乗効果がある事も分かっています。飲酒も喫煙も両方する人はリスクが約8倍に上昇し、飲酒量と喫煙量も考慮すると、最大17倍とリスクが大きく上昇することも報告されています。 副流煙も同様にリスクを高めます。
熱い飲食物による刺激も食道がんのリスクとなることも知られています。毎日、熱い朝粥やお茶を食する習慣のある方は改善が必要です。
バレット食道がん(腺がん)
- バレット食道
- 逆流性食道炎
- 肥満
日本では食道がんの数%と頻度は低いですが、欧米では食道がんの半数以上がバレット食道がんです。食生活が欧米化してきているため、日本でも今後増えてくる可能性があります。
直接の原因はまだ不明ですが、胃酸や胆汁の逆流によりバレット粘膜が炎症を繰り返し、細胞が変性すると考えられています。バレット食道がんは、バレット食道を発生母地として発症するので、バレット粘膜の存在そのものが危険因子となります。
バレット食道とは、本来は扁平上皮で覆われているはずの食道の粘膜が、胃から連続的に伸びる円柱上皮という胃の粘膜に覆われている状態をいいます。バレット先生が発見したことからバレット食道と呼ばれています。さらにバレット粘膜に腸上皮化生(胃の粘膜が腸の粘膜に分化してしまう現象)が生じた場合は、発がんのリスクが高まります。バレット食道は、3cm以上のものをLSBE(long segment Barrett esophagus)、3cm未満のものをSSBE(short segment Barrett esophagus)と2種類に分けられ、SSBEに比べてLSBEで発がんリスクが高いと考えられています。日本ではSSBEの頻度が高くLSBEはまれですが、欧米のようにLSBEが増えてくる可能性があります。
バレット食道の発生危険因子は、胃酸や胆汁の逆流によって起きる逆流性食道炎です。つまり、バレット食道そのものに対する有効な治療はありませんが、バレット食道になる前の逆流性食道炎の段階でしっかり治療を行うことが大切です。そうすることで、バレット食道を予防し、ひいてはバレット食道がんの予防につながります。
胃がん、胃腺腫
- ヘリコバクター・ピロリ菌
- 塩分
胃がんの死亡数は男女とも減少傾向になっていますが、現在でも大腸に次いで2番目に罹患数が多いがんです。
胃がんの最大の危険因子はピロリ菌感染です。未感染者と比較すると胃がん発生のリスクが約4倍あります。慢性胃炎(萎縮性胃炎)や腸上皮下生があれば最大10倍リスクが高まります。ピロリ菌が誘発する胃粘膜細胞の遺伝子異常(突然変異やDNAメチル化)が、胃がんの原因と言われています。ピロリ菌除菌は胃がんの1次予防として有効ですが、ピロリ菌感染による萎縮性胃炎がある人は、除菌治療を行っても発がんを完全に予防できるわけではなく、除菌後も胃がんは一定頻度で発生することが分かっています(年率0.4~2.0%)。また、早期胃癌の内視鏡治療後も、一定の確率で(年率2.0~2.5%)で異時多発癌が発生する事も知られています。除菌後も胃がん治療後であっても、定期的な内視鏡検査が必要です。
塩分は高血圧の原因となるだけではなく、特に男性で、胃がん発生リスクと言われています。高血圧や心血管疾患予防のためにも食塩制限が重要であり、その推奨値は1日6g未満とされています。
十二指腸がん、十二指腸腺腫
十二指腸腫瘍(がん、腺腫)の危険因子については明らかとされていませんが、腺腫の発生部位や大きさ、形状によってがん化のリスクが異なることが次第に分かってきています。また、遺伝性の家族性大腸腺腫症の場合には、高率に十二指腸腺腫・がんを合併することが知られています。胃透視(バリウム検査)で早期に発見することは困難ですので、内視鏡検査が必要になります。
大腸がん
- 赤身肉、加工肉
- 肥満・内臓脂肪
- 糖尿病
大腸がんは罹患数が急速に増加し、最も多いがんになっています。特に女性では大腸がんが1番多い死因となっています。大腸がんの殆どが、大腸腺腫と呼ばれる良性ポリープが増大し進行したものです。
大腸がんが増えている要因として、食生活が豊かになった事が挙げられ、肉類など動物性脂肪摂取量の増加、それに伴う肥満者や糖尿病有病者の増加があります。遺伝的に予測されるBMI値が1単位増加すると、大腸がんリスクが7%増加すると言う報告があります。
動物性脂肪を消化・吸収する働きを持つ胆汁酸は、大腸で分解されて2次胆汁酸となりますが、これが大腸がんの発生を促進するものと考えられています。2次胆汁酸の機能に関しては未だ十分に解明されていませんが、細胞老化や炎症応答の促進、酸化ストレスの蓄積に伴うDNA変異の誘導を介して発がん作用を呈すると言われています。また高脂肪食摂取過多は、腸内細菌叢を構成する細菌種に異常を来し、細菌種多様性の減少(単純化)や、少ないはずの細菌種の異常な増加、多いはずの細菌種の減少などが見られるようになります。この腸内細菌叢の破綻(dysbiosis)が、2次胆汁酸の産生を亢進させ、その結果として大腸がんの発生を促進させることになります。
肥満、特に内臓脂肪型肥満の人は大腸がんのリスクが高いことも分かっています。インスリンは肥満を引き起こす原因でもあり、肥満になるとこのインスリンの働きが悪くなるため、過剰なインスリンが分泌されるようになります。過食や運動不足でも、血糖値を下げるためにインスリンが大量に分泌される高インスリン血症という状態になります。過剰のインスリンはがん細胞の発生や増殖に関わる体内のシグナルを活性化させることが分かっており、発がんのリスクの1つの原因と考えられています。
糖尿病でも同様な機序で大腸がんのリスクが約2倍高いと言われています。また、内臓脂肪細胞から分泌されるレプチンというホルモンも大腸がんの発生に関係していると言われています。
肝臓がん(原発性肝細胞がん)
- 肝炎ウイルス(B型、C型)
- アルコール
- 非アルコール性脂肪性肝炎(nonalcoholic steatohepatitis: NASH)
- 肥満
- 糖尿病
肝細胞がんは男性に多い傾向にあり、男女ともに罹患数は横ばいになりつつあり、死亡数はわずかに減少傾向にあります。
肝細胞がんの多くは慢性肝炎や肝硬変といった慢性の肝臓病があり、肝細胞の炎症と再生を長期にわたり繰り返すことが、発がんの大きな原因であると言われています。
慢性肝炎や肝硬変の主な原因は、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスの持続感染(長期間、体内にウイルスがとどまる感染)及びアルコール摂取ですが、近年、肝炎ウイルス治療薬が進歩したため、ウイルス性肝炎が原因の肝細胞がんは減少傾向にあります。
しかし、肝炎ウイルス感染やアルコール摂取がない場合でも、中性脂肪が蓄積する脂肪肝があるとNASHが起こり、肝硬変、肝細胞がんが発生することが分かってきました。NASHが原因の肝細胞がんは増加傾向にあり危険因子として注視されています。NASHの病態では,TNF-α,IL-6と言う炎症性サイトカイン(細胞間シグナル伝達タンパク質)の産生亢進が示されています。炎症性サイトカインは、酸化ストレスの蓄積や修復遺伝子の抑制による遺伝子変異を促進させ、発がんに関与すると考えられています。
肥満、糖尿病の人は、NASHを発症しやすいと言われています。さらに、高インスリン血症や高血糖による酸化ストレスの蓄積、細胞内の浄化・リサイクルシステムであるオートファジー機能低下など、直接・間接的な機序が互いに複合的に関与して,発がんを促進していることが想定されています。 糖尿病有病者は約2倍の発がんリスクがあると言われています。
膵臓がん
- 喫煙
- 肥満・内臓脂肪
- 糖尿病
- 膵がんの家族歴
- アルコール・慢性膵炎
- 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)
すい臓がんは、60歳以上の男性に多い傾向があり、年齢が上がるほど発症率が高くなります。罹患数はそれほど多くはありませんが、微増傾向にあります。死亡数は、肺、大腸、胃に次いで4番目に多いがんで、消化器がんの中で最も予後不良のがん、いわゆる「難治性がん」とも「21世紀に残された最後の消化器がん」とも呼ばれています。これは、膵臓がんの大きな特徴として、早期発見が難しいためです。その理由として、①膵臓が他の臓器や血管に囲まれたおなかの深い位置にあり、検査がしにくい②進行が早いため、診断時すでに進行がんというケースがあるなどが挙げられます。
直接の原因は明らかではありませんが、生活習慣や家族歴などの様々な危険因子によって膵臓がんが発症すると言われています。喫煙は喫煙したことのない人に比べ約2倍膵臓がんに罹る危険性が高まります。肥満は20%発症リスクが高くなり、特に男性では3.5倍増加すると言われています。糖尿病歴のある人でも約2倍発症リスクが高まることが明らかにされています。大腸がんや肝臓がんと同様に、高インスリン血症等による様々な機序が関与していると考えられています。また、親兄弟に膵臓がんが発症した場合、膵臓がんになる可能性は2~3倍になります。アルコール多飲による慢性膵炎は勿論、膵臓がん発症リスクを高めます。
近年、膵のう胞疾患の中で膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)は、膵臓がんの危険因子であることがわかってきました。IPMNの発生リスクも膵がん同様、喫煙、肥満、糖尿病、家族歴、慢性膵炎、アルコールであることが判明しています。大腸ポリープと同じように、最初は、良性の小さな腫瘍ですが、時間を経て次第に大きくなり、最終的には浸潤癌になることがあります。IPMN自体が良性であっても、経過中に膵臓の他の部位に悪性度の高い膵臓がんが発生する可能性が高い事も分かってきています。膵のう胞は、健診などで偶然指摘されることがありますが、膵のう胞が認められた場合は定期的な精密検査が必要です。
もちろん、これらのファクターが必ずしも膵臓がんの発症に結びつくわけではありませんが、リスクとなる可能性はあります。日々の生活の中で、禁煙、肥満の是正、適量の飲酒などに努めることが大切です。
胆道がん(胆のうがん、胆管がん)
- 胆石
- 胆のうポリープ
- 膵胆管合流異常症
胆道がん(胆のうがん、胆管がん)による死亡数は、徐々に増加してきています。胆道がんもまたは消化器がんの中で治療が困難ながんの一つに挙げられます。その理由は、自覚症状・初期症状に乏しいことと、周囲に肝臓、胆管、十二指腸、膵臓、大腸など重要臓器が存在するため、発見された時点で周囲臓器に浸潤をきたした進行がんがあることが多いためです。
胆道がんを引き起こす特定の原因はまだ明らかではありませんが、いくつかの要因が発がんに関連していると言われています。
胆のうがんの症例の50~75%に胆石を合併することが分かっており、結石による慢性的な炎症が危険因子となります。炎症性サイトカインは、酸化ストレスの蓄積による遺伝子変異や修復遺伝子の抑制による遺伝子変異を増加させ、発がんを促進させる結果となります。また、胆汁成分の変化もがんを誘発すると考えられています。しかし、胆石がある人のうち、胆のうがんになる割合は1~3%程度と言われています。必ずしも胆石があると胆のうがんになるとは限らないため、すぐに手術する必要は無く、定期的な経過観察が勧められます。
胆のうにできるポリープのうち、腺腫と呼ばれる腫瘍は将来的に悪性化する危険性が高いことが知られています。胆のうに対しては、内視鏡的な組織検査ができないため、①10mm以上のポリープ、②増大傾向のあるポリープ、③立ち上がりがなだらかなポリープは腺腫または、がんの可能性が高いため、手術適応があります。
膵胆管合流異常症は、膵管と胆管の合流形態の異常により、膵液と胆汁の逆流が起こります。通常、胆管内圧に比べて膵管内圧の方が高いため、膵液が胆管内へ逆流します。そのため、胆管の胆汁内には活性化膵液や二次胆汁酸などの発がんのリスクとなる物質の濃度が高いことが分かっています。これにより、胆道粘膜は損傷と修復を繰り返し、炎症性サイトカインや種々の遺伝子異常の関与によって、組織学的変化を引き起こし、最終的に高率に発がんします。膵胆管合流異常症が見つかった場合には、がんが存在しなくとも予防的に手術治療を行います。